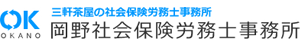弊事務所のホームページにアクセスしていただきまして、ありがとうございます。
今回は2025年4月に大きく改正される育児介護休業法について簡単にまとめました。


なお、新設の給付金については、こちらを参照してください👇
2025年4月新設!出生後休業支援給付と育児時短就業給付について
1. 子の看護休暇の見直し
【対象年齢の拡大】
これまで「小学校就学前」だった対象が、「小学校3年生修了時」までに拡大されます。
【取得事由の追加】
病気やけがの看護だけでなく、感染症による学級閉鎖や入園式・卒園式などの学校行事への参加も休暇取得の対象となります。
【勤続期間要件の撤廃】
労使協定※により「継続雇用期間6か月未満」の労働者を除外する規定が廃止され、入社直後でも休暇取得が可能となります。
週の所定労働日数が2日以下の場合は継続して除外する規定はあります。
※労使協定とは、「会社(使用者)」と「労働者の代表(労働組合など)」が話し合って結ぶ約束についての書面
2. 残業免除の対象拡大
これまで「3歳未満の子」を養育する労働者が対象でしたが、改正後は「小学校就学前の子」を養育する労働者まで拡大されます。
3. 短時間勤務制度の代替措置にテレワークを追加
業務の性質上、短時間勤務制度の適用が難しい場合、テレワークが新たな代替措置として認められます。
テレワークを導入する場合は、就業規則を変更する必要があります。
4. 育児のためのテレワーク導入の努力義務化
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるよう、事業主には環境整備の努力義務が課されます。
導入する場合は、就業規則の変更が必要です。
5. 育児休業取得状況の公表義務の拡大
これまで従業員数1000人超の企業が対象でしたが、改正後は300人超の企業にも男性の育児休業取得状況の公表が義務付けられます。
公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」となっています。
年1回、公表前事業年度の終了後おおむね3か月以内に、企業ホームページなど不特定多数の方が閲覧できる方法で公表する必要があります。
6. 介護離職防止のための措置
【個別の周知・意向確認の義務化】
家族の介護が必要となった労働者に対し、事業主は介護休業制度や支援制度の内容を個別に周知し、利用意向を確認することが義務付けられます。
周知方法は、面談・書面・FAX・メールのいずれかとなります。ただし、FAXとメールは労働者が希望した場合のみです。

【雇用環境整備の義務化】
介護に直面する前の段階から、研修の実施や相談窓口の設置など、介護と仕事の両立を支援する環境整備が求められます。
直面する早い段階の年齢というのは40歳ごろとされています。
そのため、情報提供期間としては
| ① 労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間)
② 労働者が40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間 |
のいずれかとされています。
そして、該当する労働者に対して介護休業についての制度についての情報提供をします。
周知方法は、個別相談時と同様に面談・書面・FAX・メールのいずれかとなります。ただし、FAXとメールは労働者が希望した場合のみです。
【テレワークの推進】
家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう、事業主には環境整備の努力義務が課されます。
導入する場合、就業規則の変更が必要になります。
まとめ
育児介護休業法の改正に伴い、就業規則の変更が必要となります。
就業規則の作成・変更についてお困りの企業様は、ぜひお問い合わせください。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。