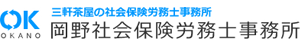弊所のホームページへアクセスしていただきまして、ありがとうございます。
共働き世帯の増加に伴い、女性側だけでなく男性側も育休を取得するよう推進されています。
そこで、2025年4月から雇用保険で育休に関わる新たな給付金が新設されます。
出生後休業支援給付


支給要件
①被保険者が対象期間※に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。
②被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。
※対象期間とは
【被保険者が産後休業をしている場合(被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合)】
産後休業期間(8週間)+8週間の合計16週間
【被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親または子が養子の場合)】
母親の産後休業期間(8週間)

支給額
最大28日間、休業開始時賃金日額×13%の額が育児休業給付金に上乗せされます。
現状、180日間は休業開始時賃金日額×67%の金額が育児休業給付金で支給されているため、最大28日間は合計で80%分受給することができます。(手取り10割相当)
これは、父母両方に支給されるものとなります。
育児時短就業給付
2歳未満の子を養育する被保険者が時短勤務をしている場合、通常よりも賃金が低下します。
その時短勤務期間中に支払われた賃金額に上乗せをする制度です。
対象者
①2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する被保険者であること。
②育児休業明け後に同一の子を育児するために時短勤務となった、または、育児時短就業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)月が12か月あること。
給付額
支給対象月に支払われた賃金額の10%が基本の支給額となります。
ただし、賃金額と育児時短就業給付を合計して、育休前の金額の90%を超えた場合は金額は調整されます。
まとめ
以上、2つが新たに設置させる給付となります。
どちらも原則事業主が申請するものとなりますので、対象の従業員なのか分からない…申請方法が分からない…などお困りの企業様はぜひお問い合わせください。