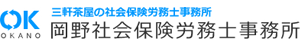弊事務所のホームページへアクセスしていただき、ありがとうございます。
今回は、6~7月に多く支給される夏の「賞与」に焦点を当てていきます。
一方で、「うちは今年出せるのか?」「公平に支給できるか?」と、経営者の頭を悩ませる季節でもあります。
今回は、中小企業で実際にあった賞与トラブルの事例と、その予防策について詳しく解説します。
そもそも賞与は「必ず支給しなければならない」のか?


ただし、以下のような状況では注意が必要です。
➡就業規則や雇用契約書に明文化せずに「ボーナスを出すのが当たり前」と社員に思われている場合、説明を行わないまま突然の減額や停止をすることでトラブルが発生することがあります。 |
⚠中小企業で実際にあった賞与トラブル【事例付き】
●事例①:成績優秀者にだけ多めに支給 → 不公平感から退職者が出た
「評価は上司のさじ加減」「何を頑張ればよいか分からない」との声が噴出。
社員間の不信感が高まり、若手社員が複数名退職。
解説:
評価基準が明文化されていなかったことが原因。賞与額に差をつける場合は、透明性のある評価制度の構築が重要です。
●事例②:売上悪化でボーナスゼロに → 説明不足で労基署に相談される
「前年まで出ていたのに、今年はいきなりゼロ」
事前説明もなく社員が不信感を持ち、労働基準監督署へ相談。
解説:
賞与の支給が「業績連動型」であるなら、就業規則にその旨を明記し、事前に説明しておくことがトラブル回避につながります。
●事例③:退職予定者への賞与を支給しなかった → 不当扱いで裁判沙汰に
「すでに退職の意思を伝えていたが、支給月まで勤務したのに賞与ゼロ」
→「不公平な扱い」と主張され、弁護士を通じた請求に発展。
解説:
「賞与支給日に在籍している者に限る」といった支給条件を明記していなかったことが原因。就業規則にしっかりと記載しておく必要があります。
✅賞与トラブルを防ぐための3つの対策
1. 就業規則に「賞与の支給ルール」を明文化する
・支給の有無、算出方法、在籍要件などを明確に記載
・「業績・勤務成績によって変動する」旨の記述が有効
2. 支給前に社員へルールと方針を共有する
・「なぜこの金額なのか」を丁寧に説明
・突然のゼロ支給や大幅減額は、事前周知と丁寧な説明で納得度を高める
3. 専門家(社労士)に相談して制度を整備する
・「うちのケースだと、支給義務はあるのか?」などもご相談可能
・トラブルを未然に防ぐルール作りをサポートします
まとめ
賞与制度を見直すことで、トラブルを防ぐだけでなく、社員の定着やモチベーションアップにもつながります。
-
「賞与を出したいが、うまく伝えられない」
-
「公平感のある支給ルールが分からない」
-
「トラブルが起きたときの対応方法を知りたい」
どんな小さな疑問でも、まずはお気軽にご相談ください。